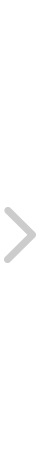東京ディズニーシーで大号泣

――声優さんにとっては日常的に起こることですが、改めて聞くととてつもなくシビアな世界ですよね……。その結果はどうだったんでしょうか?
梶:連絡があったのは、その年の事務所の営業最終日、12月27日だったと思います。留守番電話に「梶さん、とても惜しいところまで進んだんですが、今回は残念な結果となりました」というメッセージが入っていて。
初めて最終審査まで進んだオーディションでしたし、「50%の確率で受かる」と思い込み、期待も夢も勝手に膨らんでしまっていたので……結果を聞いた後は、もう落ちるところまで落ちましたね。人生で最悪の年越しでした。
その後、「いまの自分のすべてがダメなんだ」「何かを変えなきゃ」と思って、吸いもしないタバコを吸ってみたり、髪型をモヒカンにしてみたり……。
――そんなことも?! 当時の梶さんが抱いていた気持ちが、その行動からも伝わってきますね。
梶:どんな手段を使ってでも、という気持ちでした。
それから年が明け、2月頃だったでしょうか。光栄にも、また別作品の主演オーディションの話をいただいて。受けられるだけありがたかったですし、マネージャーからも「この前 惜しかったんだから、このまま頑張っていけばチャンスはあるよ」と言っていただけていたので、心機一転、気持ちを切り替えてテープを送ったんです。
すると数週間後、事務所から「合格です」という連絡があって。僕は、それを“テープオーディションに”という意味だと思って、マネージャーに「次のスタジオオーディションはいつですか?」と聞いたら「いや、今回はテープだけで決まったみたい」と。
テープだけで決まったこともそうですが、ダメだったオーディションの直後だったこともありましたし、何よりこれまであんなに苦労してきたのに、こんなにもあっさり主演が決まってしまったという事実が、本当に驚きで。
――決まるときは、何の前触れもなく突然なんですね。
梶:それに実は僕、合格の連絡をもらったとき、ちょうどディズニーシーにいて(笑)。
もちろん遊ぶお金なんてないんですけど、それこそ「遊んで気を紛らわせないとやってられない!」というドン底のメンタルだったので、気分転換のつもりで遊びに行っていたんです。でも……その合格連絡を聞いて、あまりの嬉しさに、思わずディズニーシーの中で号泣してしまいました。あれだけワンワン泣いた成人男性も珍しかったでしょう(笑)。
その後は、もはや遊ぶ気にもならず早めに切り上げ、帰り道で、その作品の原作マンガを最新刊まで大人買いして帰りました。例の如く、お金なんてないんですけどね(笑)。でも役作りには必要ですし、なにより現場に行けるチャンスが巡ってきたのが嬉しすぎて。瞬間的に金銭感覚がおかしくなりました(笑)。
いま考えると、ひとつ主演が決まったくらいでは、その後の未来なんて全然不確かなものなんですけど、それでも当時の僕にとっては、その合格一つが、自分の人生を変えてくれるはずと本気で思っていました。その時はそれくらい、「救ってもらえた」という感謝の気持ちでいっぱいでしたね。
声優の仕事が生きる活力になった

――実際にその出来事がきっかけとなって転機になっていますよね。
梶:やっぱり一つ結果が出ると、事務所からの期待値も変わりますしね。以前よりもオーディションのお話をいただけるようになりました。以降、同じようなタイミングでもう一つの主演が決まったり、レギュラー登場する役として現場に加えていただけたり、明らかにチャンスが増えました。
何よりも、声優として仕事ができる時間が増えたという事実が、僕にとって一番の救いでした。アルバイトも続けていないと到底生きていけないほどの収入ではありましたが、「アフレコ現場に行けること」が冗談抜きで生きる活力になっていたと思います。
――現場に入るようになってから、どんなふうに仕事にのぞんでいましたか?
梶:そうはいっても、生来の人見知りで恥ずかしがり屋な性格はなかなか変えられないもので、新しい現場や初めての人に出会うと、どうしても緊張してしまって、なかなか打ち解けることはできませんでしたね。まだまだレギュラーでの出演が多かったわけではないので、一度だけお邪魔した作品の現場なんかは、とくにそんな感じでした。
主演を務めさせていただいた作品では、回を追うごとに少しずつ、ほかの役者さんやスタッフさんの前でも自分らしく振る舞えるようになっていきましたけど……それでも最初のアフレコでは、台本の背表紙が手汗でボロボロになるくらい緊張していたのを覚えています。

――その緊張も、だんだんとなくなっていくんでしょうか?
梶:そうですね。やはり回数を重ねることで和らいでいった部分はあったかと思います。レギュラーとして呼んでいただけるようになったことで、自分を知ってくれている人が周りに増え、そうなってくると、今度はそんな知り合いたちが自発的にいじってくれるようになり、ひいては無理なく打ち解けるきっかけが生まれるようになっていったような気がしています。