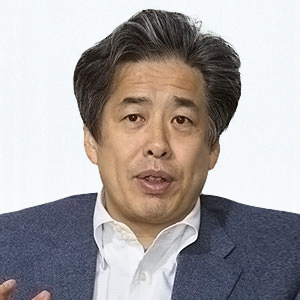2024年9月9日(月)更新
A猪木、ワールドリーグ戦初優勝
伏兵マルコフに血染めの卍固め

各国から強豪レスラーが集い、世界一を決める日本プロレスの「ワールド大リーグ戦」が始まったのは1959年のことです。1964年の第6回大会から名称を「ワールドリーグ戦」に変更し、72年の第14回大会まで続きました。14回のうち、個人的に最も思い出深いのは69年の第11回大会です。決勝でクリス・マルコフを破ったアントニオ猪木が、初めて優勝を果たしました。ちなみに猪木が「ワールドリーグ戦」を制したのは、これが最初で最後でした。
4人の優勝争い
59年に「ワールド大リーグ戦」としてスタートした「ワールドリーグ戦」は、第1回大会から第5回大会まで力道山が5回連続で優勝を果たしています。
力道山没後の64年第6回大会、65年第7回大会は、日本プロレスのエースとなった豊登が制し、66年の第8回大会からは3大会連続で“東洋の巨人”ジャイアント馬場が優勝トロフィーを手にしました。
当然、69年の第11回大会も、本命は馬場でした。それを追うのが準エースの猪木、外国人ではボボ・ブラジルとゴリラ・モンスーンの2強が虎視眈々と優勝をうかがうという構図でした。
ところが決勝に進出したのは猪木とダークホース的存在だったクリス・マルコフ。大会前、この決勝のカードを予想した者はいなかったはずです。
「ワールドリーグ戦」は、日本人と外国人の対抗戦形式で進められ、日本人と外国人の最高得点者が決勝を戦う――というルールを採用していました。
日本人は馬場と猪木がともに6.5、外国人もブラジルとマルコフが6.5で並び、優勝争いは4人にしぼられました。
69年5月16日、東京体育館。くじ引きにより第1試合は馬場対ブラジル、第2試合は猪木対マルコフの組み合わせが決定しました。第1試合は30分を戦い抜き、馬場とブラジルがドロー。引き分けは0.5点ですから、次の試合の勝者がトロフィーを抱くことになります。
抱き合う馬場と猪木
この大会が始まる前まで、初来日のマルコフの実力は未知数でした。大会が始まり、殴る蹴るを得意とするラフファイターであることはわかりましたが、クラッシャー・リソワスキーやディック・ザ・ブルーザーほど無茶をやるわけではありません。ニードロップを得意にしているとはいってもキラー・コワルスキーほどの凄味はなく、まあヒールとしては1.5流といった立ち位置でした。
それでも猪木との決勝戦は死闘となりました。黒いタイツのマルコフは、序盤からオレンジ色のタイツの猪木に襲いかかります。殴る蹴るに加え、ロープ最上段からのニードロップを何度も見舞います。
猪木を場外に落とし、いす攻撃、さらには机に額を打ちつけるなど、やりたい放題。猪木の反撃にあって形勢が不利になると、タイツに隠し持っていたセンヌキで喉元や額を突くのですから、まるで始末に負えません。
いつの間にか猪木の額は鮮血で真っ赤に染まります。それでも死力を振り絞ってセンヌキを奪い取り、マルコフを殴りつけると、場内は「ワッショイ、ワッショイ」の大歓声。最後は卍固めでギブアップを奪い、初載冠に成功したのです。
元週刊ゴング編集長の小佐野景浩さんは、猪木優勝の背景として、「すでにNETでの放送開始が7月からと決まっていたので、それに向けて猪木を箔付けしようという意図があったんでしょうね」(『馬場・猪木をもっと語ろう!』小佐野景浩・二宮清純、廣済堂新書)と語っていました。
優勝決定直後のリングには馬場の姿がありました。猪木が馬場に抱きつくと、馬場は猪木の肩をパンパンと叩きながら、初優勝を称えていました。

二宮清純