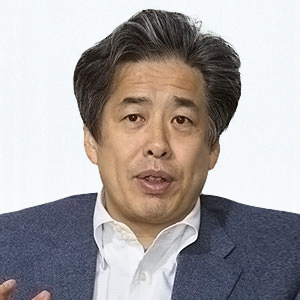2023年2月13日(月)更新
悪の限りを尽くした“怪人”ザ・シーク
“ジキル&ハイド”演じ続けたヒール魂

この男がリングで流した血は、生涯でいったいどれくらいになるのでしょう。ザ・シーク=大流血戦。悪の限りを尽くしたレスラー人生でした。
坂口征二を血祭りに
“アラビアの怪人”と呼ばれたシークはレバノン系アメリカ人と言われています。ナイフ、フォーク、釘、ロープ、先の尖ったシューズなど身の回りにある、ありとあらゆるものを凶器に変えたシークですが、とりわけショッキングだったのは“火炎殺法”です。日本のリングで、相手に向かって炎を浴びせかけたのは、おそらくシークが最初ではないでしょうか。
この人、リングに上がるとアラーの神にお祈りを捧げるのですから、おそらくはイスラム教徒だったのでしょう。でもレバノン系はキリスト教徒も多かったため、実際のところはわかりません。シークの悪党たる所以は、神聖なお祈りの最中でも、相手のスキを見て急所蹴りを見舞ったりすることです。全くもって油断もスキもありませんでした。
シークのタイツの中には、帯に凶器が隠されていました。レフェリーはいったい、何のためにボディチェックを行っていたのでしょう。
長い間、プロレスを見てきましたが、試合前のボディチェックでレフェリーが凶器を発見した例はあまり知りません。単なるセレモニーとはいえ、今になって思うと、あれは不思議な光景でした。
シークと言えば思い出すのが、1972年9月に行われた坂口征二とのUNヘビー級タイトルマッチです。末期の日本プロレスが社運を賭けて招聘したのがシークでした。
6日、東京・田園コロシアムでの試合。挑戦者のシークはゴング前から大暴れし、コミッション役員が持っていたタイトルマッチの認定書を口で引きちぎり、そのまま食べてしまったのです。すなわちシークは認定書という権威までコケにしてしまったのです。
「徹底した二重人格」
タイトルマッチは結局、大流血戦の末、シークが2対1で勝利し、坂口から王座を奪い取りました。まともな技といったら、1本目をとったキャメルクラッチくらい。ラクダの産地である中東系のレスラーがこの技を得意としていたのは、民族性のアピールだったようにも思われます。
晩年のシークを日本に招いたのがFMWを立ち上げた大仁田厚でした。1991年11月のことです。「70歳近いレスラーを呼ぶなんて」との批判もありましたが、大仁田はどこ吹く風でした。
その大仁田にシークの印象について聞くと、こんな感想が返ってきました。
「シークというのは徹底した二重人格ですよ。リングの中の人格と外の人格を完璧に使い分けている。リングの中に入ったら、アイツは本当に人を殺す気なんだから。あのカール・ゴッチですら、シークの報復を恐れて何もできなかったんだからね。それに彼は生涯一ヒールでしょ。アブドーラ・ザ・ブッチャーやタイガー・ジェット・シンみたいに、途中でベビーフェイスになるようなことはしなかった。いくら歳を取っても、自分の生き方を曲げないんだからね。敵ながらあっぱれだよ」
1960年代中盤以降、シークはプロモーターとしても名を馳せ、デトロイトに君臨していました。レスラーとしてはNWA・USヘビー級王者となり、ジョニー・バレンタインやボボ・ブラジルらと抗争を繰り広げていました。
宿敵のブラジルに対しては、こんな“禁句”を口にしています。
「ブラジルの黒い肌を見ると、何もかも忘れて噛みついてやりたくなるんだ」
今読み直しても背筋が寒くなってきます。

二宮清純