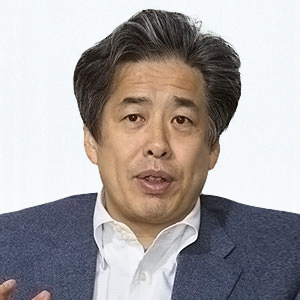2022年12月12日(月)更新
“東洋の神秘”グレート・カブキ
T・J・シンと異色のケンカマッチ

本名の米良明久、出身地にちなんだ高千穂明久を名乗っていた頃は地味なレスラーでした。しかし米国で歌舞伎役者風のメイクを施したザ・グレート・カブキに変身してから、彼の人生は激変します。“東洋の神秘”というニックネームが、これほどぴたりと当てはまるレスラーはいませんでした。
女房に「バカなこと言うな!」
米国から“凱旋帰国”を果たしたカブキさんに初めてインタビューしたのは1983年2月のことです。般若の面を付けた連獅子姿で入場し、ヌンチャクを自在に操りながら、“毒霧”をフーッと吹き上げる姿は、もうそれ自体がミステリアスで、米国で大ブームを巻き起こしていたのも納得でした。
もともとカブキさんは正統派のレスラーでしたが、身長180センチ、体重100キロちょっとの“ポッチャリ体型”だったため、人気は今ひとつでした。
そこに現れたのがマネジャー兼ブッカーのゲーリー・ハートでした。
「あれは1980年春のことだよ。突然、ゲーリー・ハートからカリフォルニアの自宅に電話がかかってきたんだ。その内容はというと、“歌舞伎の格好をしてリングに上がってくれ”と。でも彼はアメリカ人だから、実物の歌舞伎を見たことがない。そこで、とりあえず歌舞伎風のマスクを被ってやろうということになったんだ。
ところが、偶然、その話を横で聞いていた女房が“アナタ、歌舞伎でやるんだったら、顔にペイントしなきゃおかしいじゃない”っていうわけ。最初は女房に“バカなこと言うな!”って言ったんだけど、よくよく考えてみると女房の言う通りなんだ。それが今のスタイルになったきっかけなんだ」
歌舞伎スタイルの採用が、ゲーリー・ハートのアドバイスによるものだとは聞いていましたが、まさか奥さんの指摘を受けてペインティングをするようになったとは……。これぞ内助の功でしょう。
カブキさん、こんなことも言っていました。
「結局、高千穂のままだったら、オレのプロレス人生は終わっていただろうね。あのね、人間、転機に際しては2つのタイプがあるんだ。ひとつは、これ以上、どうしようもなくなって、“もう、どうにでもなれ”と開き直るタイプ。もうひとつは、現状に満足せず、さらに理想に向かって努力しようとするタイプ。オレの場合は前者だったね」
毒霧vs急所打ち
しかし、単にペインティングを施し、東洋風のギミックを用いただけでは、トップレスラーにまで上り詰めることはできません。カブキさんは高千穂明久時代に用いていた左のアッパーカットとトラースキックに磨きをかけ、“東洋の神秘”にリアリティをもたらせることに成功したのです。
83年2月25日、愛知県体育館で行われたタイガー・ジェット・シンとの一騎打ちは、プロレスをエンターテインメントとして見た場合、最高傑作のひとつと言っていいでしょう。
暗闇の中、つつみの音とともに鎧兜を身につけ、花道をゆっくりと歩くカブキさん。手には“真剣”が握り締められています。千両役者そのものです。
反対側からサーベルをくわえた“インドの凶虎”シン。金髪の上田馬之助さんを従えています。
いきなり突っかけたのはシン。ゴングが鳴る前にカブキさんに襲いかかり、ターバンで首を絞め上げます。そこからは殴る、蹴る。そして得意技のコブラクロー。隈取りを施したカブキさんの表情が苦痛に歪みます。
しかし、カブキさんもやられっぱなしではありません。左のアッパーカット、トラースキックで反撃を開始し、シンと互角に渡り合います。
その後、リングに突き落とされたカブキさん、エプロンで“毒霧”を吹きかけ、再び反撃に転じます。目には目を、とばかりにシンは急所打ち。両者がもみ合っている最中、シンのパンチがレフェリーのジョー樋口さんにヒットします。それでも掴み合ったままの2人に、レフェリーは“両者反則”のコール。結局、試合は痛み分けに終わりました。
トップヒールとして長きに渡って日本のリングを荒らし回ったシンが、カブキさんの控室を襲うなど目の仇にしていたのは、一目も二目も置いていたことの証明だったのではないでしょうか。

二宮清純